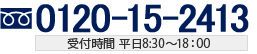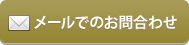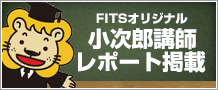用語集

さ

サーキットブレーカー制度 【 さーきっとぶれーかーせいど 】
先物価格が急激な乱高下を起こし、理論価格から一定の幅を超えた場合に、取引所が一時的に取引を中断し、先物の過度の乖離を抑制する制度。


債権格付け 【 さいけんかくづけ 】
債権が償還を迎える前に債務不履行に陥るリスクを調査し、記号で表したもの。格付け会社で有名な所としては米国に本拠地を持つムーディーズやスタンダード・プアーズなどがある。


歳出 【 さいしゅつ 】
国が公共事業や福祉事業、公務員の給与などのためにお金を出す行為のこと。


財政収支(米国指標) 【 ざいせいしゅうし 】
法人所得税や個人所得税などの歳入と、国債の利払いなどの歳出が中心となっており、米国の指標の中でもかなり注目されている指標の一つとなっている。基本的には前年の同月値と比較されることが多い。


裁定取引 【 さいていとりひき 】
複数銘柄間・異市場間・同銘柄異限月間などの価格差を利用して、売り買いのポジションを組み合わせて商いをし、収益を見込む取引
【同意語】 鞘取り、アービトラージ、ストラドル取引、スプレッド取引。


歳入 【 さいにゅう 】
国家財政の年間収入のこと。主に税収入(直接税と間接税)から成り立っている。
国家の財源である税収入を増やしたい時には、影響の少ない間接税(消費税など)の税率を変更する方法がある。直接税となる所得税率や法人税率を高くすると、家計や企業活動に大きな影響を与えるので慎重になる。


歳入欠陥 【 さいにゅうけっかん 】
年度決算時に、歳入よりも歳出が多いような状態をさす。このように不足金が発生した場合には、新規の国債を発行したり、他の特別会計などを使って穴埋めする事となる。


債務超過 【 さいむちょうか 】
資産の額よりも債務(借入金)の額の方が多い状態のこと。


債務不履行 【 さいむふりこう 】
債権などの借入金の元金が支払えなくなること。


材料 【 ざいりょう 】
相場を動かすもととなるもの。経済問題や、政治問題、商品の需給事情、或いは市場内部の売り方と買い方との力関係のこともある。


差益 【 さえき 】
売り買いをして出た利益のこと。
【反意語】 差損


酒田五法 【 さかたごほう 】
江戸時代、米相場で巨万の富を築いたと伝えられる本間宗久が考案した日本古来の罫線解釈法。五法とは『三山』、『三川』、『三空』、『三兵』、『三法』のこと。
 【参考】FITSテクニカル指標一覧
【参考】FITSテクニカル指標一覧


先限 【 さきぎり 】
限月の先のものをいう。一番新しい限月。


先物 【 さきもの 】
1)先物取引の略称
2)先物取引の対象となっている商品(現物と対比した呼び方)
3)期先限月のこと


先物取引 【 さきものとりひき 】
商品の受け渡し決済期日がくる前に転売買戻しによって差金決済できる取引。


差金 【 さきん 】
売買を行ったときの売った金額と買った金額との差額のこと。


差金決済 【 さきんけっさい 】
商品の受け渡しを行わず、売り・買いしたものを買戻し・転売によって取引を終了すること。売ったものが値下がりし買い戻せば利益となり、値上がりし買い戻すと損失となる。又、買ったものが値上がりし転売すれば利益となり、値下がりし転売すると損失となる。


作況指数 【 さくきょうしすう 】
作柄状況を表す指数。前七ヵ年の作柄が、最良の年と最悪の年とを除いて、五年間の平均収量を算出し、作況指数はこれを100で表す。


作付面積 【 さくづけめんせき 】
農作物を作る面積のこと。生産者は前年の成績や売上、或いは作付期直前の価格などにより、作付を減らしたり増やしたりする。


下げ足 【 さげあし 】
下げていた相場が、ちょっと底をついた感じとなり、まだ下げそうでも案外下がらない状態を指して言う。


下げ渋り 【 さげしぶり 】
為替相場の決定理論の一つで、二国間の金利差に注目する。例えばアメリカの金利が日本の金利を上回ると、円を売ってドル資産に替える動きが出るというように、為替レートが貿易取引の決済によるものではなく、資本の動きによって決定されるという理論。


指値 【 さしね 】
売買契約や決済を行うときに値段を指定して注文を出す方法、またはその値段。


指値注文 【 さしねちゅうもん 】
値段を指定して発注する注文。
買いの指値注文は、指定値段以下で買いたいという注文。売りの指値注文は、指定値段以上で売りたいという注文。
(株)東京商品取引所ではLO-FaSがそれに当たる。
 注文の種類・約定条件
注文の種類・約定条件


差損 【 さそん 】
売り買いをして出た損失のこと。
【反意語】 差益


雑所得 【 ざつしょとく 】
公的年金、原稿料、印税、講演料、謝礼金などの他の所得にあてはまらない所得。為替取引の売買差益金などがこれにあたる。年収2000万円以下の給与所得者の場合、20万円までの所得に関しては非課税扱い。


鞘 【 さや 】
限月間、銘柄間、取引所間などの価格差のことをいう。
【同意語】 値鞘、スプレッド


鞘出世 【 さやしゅっせ 】
通常、逆ざや(期近が期先より上ザヤ)で、限月が繰り上がるごとに価格が高くなっていくこと。
【反意語】 鞘滑り


鞘滑り 【 さやすべり 】
大きかった鞘が小さくなること。又は、順ザヤ銘柄で、期近に回るごとに価格が安くなっていくこと。
【反意語】 鞘出世


鞘取り 【 さやとり 】
複数銘柄間・異市場間・同銘柄異限月間などの価格差を利用して、売り買いのポジションを組み合わせて商いをし、収益を見込む取引
【同意語】裁定取引、アービトラージ、ストラドル取引、スプレッド取引。


ザラバ 【 ざらば 】
複数約定決済の取引。
競売買による値段を決定する方法のひとつで、価格優先の原則、時間優先の原則により、多数の売り方と買い方が互いに値段を競い、そのうち値段と数量とが合致した者が、個々に相対で売買を成立させる方法のこと。

し

地合い 【 じあい 】
相場の状況を表す言葉で、相場状況が良い場合には「地合いが良い」。相場状況が悪い場合には「地合いが悪い」と言う。


時間優先の原則 【 じかんゆうせんのげんそく 】
同値で出された指値注文は、先に出された注文を優先して成立させると言う優先順位のこと。


仕切り 【 しきり 】
買い建玉を転売、売り建玉を買戻しして、売買を終了させること。
【同意語】 落ち、手仕舞い


仕切り決済 【 しきりけっさい 】
建玉を買い(買い建玉)で持っていれば売り、売り(売り建玉)で持っていれば買い戻しを行う事によって終了、処分すること。


仕切値 【 しきりね 】
転売・買戻しした値段。
【反意語】 落値
【反意語】 建値


自己玉 【 じこぎょく 】
商品取引業者は自社の利益を目的として自己売買を行うが、その建玉のこと。


自己資本比率 【 じこしほんひりつ 】
企業の総資本に占める自己資本の割合。この自己資本比率が高ければ、他人資本(=負債)が少ないことを意味し、企業体質の強さ・安全さを示す。


自己売買 【 じこばいばい 】
証券会社や銀行などが、自己の計算で株式や債券、為替などの金融商品を売買(投資)すること。ディーリングともいう。


しこり玉 【 しこりぎょく 】
安値で売った後に相場が上がり、又は高値で買った後に相場が下がって、損計算となっているために、仕切るに仕切れなくなってしまった建玉。しこり玉が多い取組内容は、一般的に踏みによる急騰、投げによる急落の可能性を潜在的に秘めており、値幅が大きくなりやすい。
【同意語】 因果玉


市場介入 【 しじょうかいにゅう 】
中央銀行がある目的をもって(円安にしたい、円高にしたい等)市場に参加し、大量の資金を使って行う取引。


市場リスク 【 しじょうりすく 】
市況変動などによって資産や負債等の価値が変動するリスクのこと。市場リスクには、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクの三つのリスクがある。


システミックリスク 【 しすてみっくりすく 】
金融機関や証券会社が何らかの理由で決済不履行となった場合に、その不履行によって他の金融機関が不履行に陥るといったように、1つの金融機関の不履行が連鎖し、全体が麻痺するようなリスク。


下押す 【 したおす 】
相場が安くなることをいう。


下支え 【 したざさえ 】
相場が下落しそうで下がらないこと。下落しそうなとき、強い材料が潜んでいて下がらないことがある。または買い方が資金力にものをいわせて、次々と買って下落させずに、買い材料の出現まで頑張ること。


下値 【 したね 】
値段の安いところ、または下落幅。
【反意語】 上値 。


下値追い 【 したねおい 】
引き続いて値下がりし、その値を追いかけるように一段と売気が盛んになること。
【反意語】 上値追い


市中相場 【 しちゅうそうば 】
取引所以外の取引によって付けられた相場のことで、場外相場、店頭相場ともいう。貴金属のローカル市場(ロコ市場)などは、しばしば先物価格に影響を与える。


確り 【 しっかり 】
相場が堅調で、少々高いこと。


実効為替レート 【 じっこうかわせれーと 】
表面上の為替レートだけでは判断しきれない各通貨ごとの対外競争力を単一の指標で総合的に捉えたもの。
日銀調査統計局が発表する円の実効為替レートは、円と主要通貨の為替レートを各国別の輸出金額等による貿易ウエイトで加重平均し、1973年3月を100とした場合の指数で表した「名目実効為替レート」と、各国の物価上昇率を調整した「実質実効為替レート」がある。


実質金利 【 じっしつきんり 】
物価変動の影響を考慮し、「名目金利」から物価上昇率を差し引いた実際の金利。


実質GDP 【 じっしつじーでぃーぴー 】
本当の財の価値を算出するため、物価変動の影響を取り除いたもの。


実需 【 じつじゅ 】
実際にある需要のこと。


仕手 【 して 】
大口の注文を出すことにより、相場の値動きを左右し収益を狙う投資家。


指定替え 【 していがえ 】
東京証券と取引所の市場第1部に指定されている銘柄が、市場第2部に指名されること。


指定倉庫 【 していそうこ 】
取引所が現物の受渡し場所として指定する倉庫のこと。指定倉庫在庫が定期的に発表される銘柄(ゴム、小豆、等)では、在庫の増減が先物価格に影響を与えることがある。


仕手株 【 してかぶ 】
短期的に大きな利益を得ようとする投資家が好んで売買する株の銘柄。一般的に資本金が小さくて発行済み株式数が少ないものの、市場に出回っている株が多い小型株がターゲットにされやすいようです。


仕手相場 【 してそうば 】
仕手集団による売買を背景に激しい値動きをする相場のこと。


地場 【 じば 】
取引所の会員、会員の従業員、又は常時会員の店に出入りして相場を張る玄人の相場師を指し、その手口は、一般の委託者、商社などと区別され、注目されることもある。
【同意語】 地場筋


地場受け 【 じばうけ 】
その他の証券会社などから注文を受ける事。自社で受ける事が出来る注文をわざわざ他の証券会社に流すと言うことは、顧客の資金の横領などの危険性もあるため、定款によって禁止されている。


資本金 【 しほんきん 】
株主から払い込まれたお金の内、会社が資本金としたもの。


資本収支 【 しほんしゅうし 】
国家間の直接投資や証券投資などの資本取引の収支。


週間足 【 しゅうかんあし 】
一週間を1単位として書く罫線。略して週足(しゅうあし)。週間足は一般的に、中期的な価格の傾向を読むのに適しているとされている。
【参照】日足


十字線 【 じゅうじせん 】
チャート上に見られる、始まりと終わりが同じ価格で終了することを表す寄引同事線の一種。


住宅着工件数(米国指標) 【 じゅうたくちゃっこうけんすう 】
米国における月中に建設された新設の住宅戸数。発表される数値は季節調整済みの年率換算したベースとなっている。
新築の家を建てると言うことは、その中で暮らすための生活必需品を新たに購入するということとなり、景気循環の面からも重要視される指標の一つとなっている。


充用 【 じゅうよう 】
委託証拠金として、現金の代わりに預託された有価証券のこと。
銘柄によって、評価される割合が異なるが、時価総額を上回ることはない。
【同意語】 代用


需給相場 【 じゅきゅうそうば 】
需要と供給の関係を背景に推移する相場のこと。


受託会員 【 じゅたくかいいん 】
商品取引所の加入会員のうち、当該商品市場における取引の委託を受けることの許可を主務大臣から受けた商品取引員である会員のこと。


順鞘 【 じゅんざや 】
受け渡し期日が近い限月の値段が安く、遠い限月になるにつれて値段が高くなっている状態のこと。
一般的に「順鞘に買いなし」などと、売り方有利といわれる。
【反意語】 逆鞘


順張り 【 じゅんばり 】
相場が上がりそうな時に買い、下がりそうだったら売る、と言うように相場の流れに沿って売買する方法。「逆張り」と反対の意味。


証拠金 【 しょうこきん 】
【参照】取引証拠金


証拠金取引 【 しょうこきんとりひき 】
少額の資金を取引業者に預託する事で、預託した資金以上の取引を行う取引。
例えば、1万ドルの取引を実際に行う場合、($1=¥110)110万円の資金が必要となります。しかし、取引業者が定めた証拠金、8万円(業者によって異なる)を預託することによって、1万ドルの運用をする事が可能となる。


上場 【 じょうじょう 】
取引所において取引すること。


上場商品 【 じょうじょうしょうひん 】
取引所において取引が行われている商品。


上場銘柄 【 じょうじょうめいがら 】
証券取引所で会社の株式の売買を認められた株式のこと。売買を認めてもらうためには基準があり、この基準を満たさないと上場できない。上場すると社会的認知度が上がる。


上伸 【 じょうしん 】
上昇している相場がさらに上昇すること。


消費者信頼感指数 【 しょうひしゃしんらいかんしすう 】
消費者に対し、現在の景況感、雇用判断、そして半年後の景況感、雇用判断、所得に対する楽観、悲観についてのアンケートを元に作成された指数。


消費者物価指数 【 しょうひしゃぶっかしすう 】
一般消費者の家計支出の中で、日常的に購入する商品とサービスの小売段階での値段の動きを表す指数で、毎月、総務庁統計局から発表される。一般の世帯の消費生活に必要な支出が、物価の変動によってどのような影響を受けるかがわかる。


商品取引業者 【 しょうひんとりひきぎょうしゃ 】
主務省の許可を受けた商品取引所の会員。


ショート 【 しょーと 】
為替取引においてポジション(持ち高)を保有する際に、ある通貨が他通貨に対して売り越しの状態にあること。買い越しにある場合には、ロング、売り買いのバランスが取れていて為替リスクがない状態をスクエアという。例えば米ドル・日本円の取引で、円を売っていれば円・ショート(ドル・ロング)となる。


ショートポジション 【 しょーとぽじしょん 】
為替や株式の取引において、新しく売りの建玉を作ること。「ロングポジション」と反対の意味。新規売りの建玉を買戻して決済することをショート・カバーという。


所得税 【 しょとくぜい 】
それぞれの個人の所得に対して課税される税金。会社などの収益に対して課税される税金は「法人税」と言う。


新規失業保険申請件数(米国指標)【しんきしつぎょうほけんしんせいけんすう】
米国内における失業者が、初めて失業保険を申請した件数を集計したもの。米国では失業問題が大きくなっており、為替の動向をうらなう上でも重要な指標と言える。


新規建玉 【 しんきたてぎょく 】
新たに建玉すること。


申告分離課税 【 しんこくぶんりかぜい 】
他の所得と区分して課税される方法。株式の売買益などがこれにあたり、譲渡所得(売却益)に対して26%の税率で終了する。


新値 【 しんね 】
これまでなかった水準の値段を指し、新しい高値を新高値、新しい安値を新安値という。一般的に、相場の目標として意識されやすい。


新甫 【 しんぽ 】
納会後、新しく生まれる限月のこと。


信用取引 【 しんようとりひき 】
投資家が証券会社に委託保証金を預託することにより、買い付け資金や売付株式を借りて行う取引。投資家が十分な資金や証券を持っていない時に有効。
信用取引には株式市場の流動性を高める役割がある反面、仮需を生み出し、市場形成を不安定にする場合もある。わずかな手持ち資金で大きな取引が可能となる反面リスクも高まる。


信用リスク 【 しんようりすく 】
外貨預金などを扱っている銀行や、外国債券を発行している企業や政府機関などが経営破綻に陥って、預金や債券の元利金返済に支障をきたすリスクのこと。このリスクを回避するためには、事前に債券格付けなどをチェックする必要がある。

す

スイングトレード 【 すいんぐとれーど 】
数日間での短期売買のこと。または、ある程度の利幅を狙う手法のこと。スキャルピング手法よりも期間、値幅は長めである。


スキャルピング 【 すきゃるぴんぐ 】
デイトレードの手法で、わずかな利幅を狙って短時間で売買を繰り返すこと。スカルプとはもともと敵の皮をはぐという意味で、最近ではデイトレード手法の用語として用いられている。


スクイズ 【 すくいず 】
買い方が現物を引き取る態度を明らかにし、売り方、特に空売り筋を窮地に陥れて、踏み上げさせようとする戦法。期近限月独特の乱高下する商いの原因となる。
【同意語】 玉締め


ストップ・ロス 【 すとっぷろす 】
保有しているポジションに対して、実際の相場が思惑と反対方向に変動して評価損が発生した場合に、損失額を一定の範囲内に抑えるために出す逆指値注文のこと。通常の指値注文とは逆に「いくら以上なら買い」「いくら以下なら売り」という注文の設定がされる。


ストップロスオーダー 【 すとっぷろすおーだー 】
損切りする値段を予め決めておき、逆指値、又はIRO注文を出すこと。正しいストップロス注文を出しておけば、無駄な損失を出してしまうことが防げる。


スプレッド 【 すぷれっど 】
限月間、銘柄間、取引所間などの価格差のことをいう。
【同意語】 鞘、値鞘


スプレッド取引 【 すぷれっどとりひき 】
二つの同一証券・商品の金利差や価格差を利用して利益を得ようとする取引。


スペキュレーション 【 すぺきゅれーしょん 】
差金決済を前提にし、利ざやを稼ぐことを目的に取引すること。
【同意語】 投機


スペキュレータ 【 すぺきゅれーたー 】
投機家のこと。


スポット 【 すぽっと 】
直物(じきもの)取引。契約成立から2営業日以内に決済される取引で、外国為替の場合、一般に新聞テレビ等で報道される為替相場は銀行間で売買されたこの取引のレートのことを指す。

せ

政策金利 【 せいさくきんり 】
民間金融機関が中央銀行から必要資金の融資を受けるときに適用される金利。
「公定歩合」と呼ばれる。


政策投資 【 せいさくとうし 】
企業が株式を売買することによって利益を得ようとするのではなく、その株式を保有する事によって事業面でのプラスや、相手との関係強化などを目的とする投資。


成長株 【 せいちょうかぶ 】
将来、企業業績が期待される株式。


製品輸入比率 【 せいひんゆにゅうひりつ 】
輸入総額から食料品、木材、鉄鉱石、燃料などを除いた品目が輸入総額に占める割合。日本は天然資源に乏しいため、海外からの輸入総額のほとんどが原油や天然ガスだったが、80年後半になると急速に円高が進み、製品輸入の割合が51%前後と膨らんだ。


政府経済見通し 【 せいふけいざいみとうし 】
翌年の日本経済の動きを政府が予測して発表するもので、経済の先行きをうらなう上でも重要な材料となる。


整理商い 【 せいりあきない 】
買われたものはいつか売られ、売られたものはいつか買い戻されるため、買って(売って)いるポジションを一回仕切り、ポジションを減らすこと。
【同意語】調整


セーフティーネット 【 せーふてぃーねっと 】
発行時に利率や償還額が確定されていない、金利リスク以外のリスクを組み入れた債券。オプション取引などを使って一定の条件下での高利回りを可能にするなど投資ニーズに応じた様々な商品設定ができる。


世界銀行 【 せかいぎんこう 】
発展途上国に対する民間の投資や融資を支援する国際機関。
特に通信・健康・潅漑などのインフラストラクチャー分野での支援を行う一方で、被援助国に対してはその経済構造を変化させるように要求することもしばしばある。ワシントンD.C.に本部を置き、国際復興開発銀行(IBRD:International Bank for Reconstruction and Development)ともいう。


責任開始期【年金・保険関連用語】 【 せきにんかいしき 】
保険や年金などの契約を行った際に、その契約が有効となる期日のこと。


石油輸出国機構 【 せきゆゆしゅつきこう 】
産油国の内11カ国が加盟しており、原油生産量を調節して原油価格の安定を図ったり、そのための手段を構築する機関。OPECとも呼ばれている。


全国銀行貸出残高 【 ぜんこくぎんこうかしだしざんだか 】
銀行による企業や個人に対する融資の残高を集計したもの。景気が良くなってくると資金需要が増えるため貸出残高が増え、不景気になってくると資金需要が低迷するために貸出残高は減ってくることが多い。


全値押し 【 ぜんねおし 】
相場の動きで、一旦上昇した相場が元の位置まで戻ってくる事を指す。上昇した半分の値位置まで戻ってくる事は半値押し、若しくは半値戻しと言う。
【同意語】往って来い

そ

総崩れ 【 そうくずれ 】
相場が暴落すること。


総合課税 【 そうごうかぜい 】
所得者が、多方面から所得がある場合に、1つ1つの所得に対して課税するのではなく、全ての所得を合計した合計額に対して課税される方法。


増資 【 ぞうし 】
会社が新たに株式を発行し資本金を増やすこと。資本増加の略称。
資金調達のために新株を発行する有償増資には、特定の対象者に向けた割り当て募集と、不特定多数の一般投資家を対象とする公募による増資がある。


総取組高 【 そうとりくみだか 】
全建玉数、売買契約の合計。1枚売りと1枚買いを合わせて1取組と数える。


相場つき 【 そうばつき 】
相場の流れ、様子、相場の動き方のこと。


底 【 そこ 】
相場が下がりきったポイント。
【反意語】 天井


底入れ 【 そこいれ 】
相場が底をついたこと。


底堅い 【 そこがたい 】
相場が下がりそうに見えて、案外下がらず、むしろ確り気味である様子。


底を打つ 【 そこをうつ 】
相場が下落して下がる所まで下がり、下げ止まった状態をさす。


損益分岐点 【 そんえきぶんきてん 】
売上から、その売上を得るために必要とした費用を差し引いた時に±0になるような分岐点のこと。この分岐店を超えると利益が生まれ、下回ると損失が生まれる。


損切り 【 そんぎり 】
損を承知で建玉を反対売買により手仕舞うこと。
【反意語】 利食い